���{���̓Ǐ���
�E��������߂���˂�i���×��q�����A�����ُ��X�j
�E�͂��������������̂����� �t�H�A���� B����u����x�݂̂͂Ȃ��v
�ł�������ł́A2����1���̂��Z50�₪����̃e�X�g�������B�W������6���Ƃ��邩��A1���7�b���炢�œ�����v�Z���B���q�́A�����т����Ȃ��������e�X�g�̊��ɂ́A1���5�b�œ������Ă����̂ŁA����̒P���͏����ł����悤���B
���{���̓Ǐ���
�E��܂Ȃ����� ���{����G�{�V���[�Y�����������̘b�́A�܂��܂��ǂݕ��������Ă�����������ł��B���낢��Ȗ{����������ǂ�ŁA�������̂ɐ��ݓn��悤�ɁB�B�B
4���̎������Ԃ�65���B����肱�ꂪ��肾�B�֎q�̏�ɍ��葱�����鎞�Ԃ��ǂ����H
�����č������߂Ẳߋ���B�����Ŗ�肪���サ���B���q�͒Z�C�L�������B�u�W�������������ă��A���[���������āE�E�E�v�Ƃ������ނ��̘b�́A�����ɊW�Ȃ����Ƃ��đS�������������Ȃ��B������A���Ɏc��Ȃ��܂ܕ��������Ă��܂��B���ꂪ�w�ƂȂ��āA���̎�̎���ɓ������Ȃ��̂��B
�u�����������āA�ߌ�ɂ́������܂����B���āA�ߑO�ɂ͉��������ł��傤�H�v�ƂȂ�ƁA�u�����A�Ȃ�Č����������H�v�ƍQ�Ă�B�����ăt�@�@�[�t�@�@�[�����n�߁A���������Ԃ�����Ă���̂�������Ȃ��Ȃ�A�Ƃ���������B�g�s�b�N��1���Ɠ�������̂����A2�̏o�����ɂȂ�Ɠ������Ȃ��B
�Ⴆ�A�u���ꂳ���������ĉ��ς����āA�ߌ�ɂ͗X�ǂ֍s���܂����v�ƌ����Ă��A������������b���Ƃ��u���ꂳ��́E�E�E���A����āE�E�E���ς�h���āE�E�E�v�Ƃǂ������B�Ƃ��낪�u���ꂳ��͖����̒��w�Z�֓ǂݕ������ɍs���āA�ߌ�ɂ͔������֍s���܂��B�v�ƂȂ�ƁA�ǂݕ������͑��q�ɂƂ��Ă͑厖�ȗp���Ȃ̂ŁA��ΖY��Ȃ��B
���`�A����Ȃ��ƂɂȂ�Ƃ͗\�z���Ă��Ȃ������ȁB�ǂ����悤�H�H�H����̉p���B
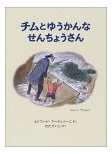 ���{���̓Ǐ���
���{���̓Ǐ���
�E�ӂ����E�т�����!? ���ǂ��}�� ������
�E�ǂ� �������̂Ƃ�����W
�E�`���Ƃ䂤����Ȃ��傤����\�`���V���[�Y�q1�r������͗ǂ��G�{�I�j�̎q�̖`���S����ɂ������Ă܂��B�G�h���[�h �A�[�f�B�]�[�j�Ƃ����C�M���X�̍����I�C���X�g���[�^�[�̑}�G���ǂ��ł��B����ȑ�l������Ǝ��ł������������I�Ǝv���قǁA�D������͗E���ł��B
�E�J�k�[�͂܂� �~�Z�X���ǂ��̖{
�EWho Lives Here? (Emergent Reader Science; Level 2)
���{���̓Ǐ���
�E�����b�v�X�̂킭�킭��`�� (2) �����}���فE���w�̕���
�E�L���O�q�t�̗͂Â悢���Ƃ\�}�[�e�B���E���[�T�[�E�L���O�̐��U���A�����J�Ŏ�����̒��ŁA�������������Ƃ��Y�ꂸ�ɂ��Ăق����Ǝv���܂��B
�����͐U�x���������̂ŁA������f�̂��ߎ��ȂƊ�Ȃ֍s�����B
���Ȃ̕��́A�����͂Ȃ������C�����܂��Ă���Ƃ̂��ƂŁA���C������Ă��炢�A�t�b�f�h�z�Ŋ����B��1�Œ�����f�ɗ��Ă��������A�ƌ�����B�w�Z�ȊO�̎��Ȍ��f�́A�Ȃ��3�N�Ԃ�Ȃ̂ŁA��قǑӂ��Ă���Ǝv��ꂽ�̂��낤���B�u���̕a�@�łȂɂ����̎��Â����Ă��炢�܂������H�v�ƃ`�F�b�N������A�����u�������v���ē��������������̂˂��B���̎��Â��������ǂ����́A������������ɕ�����Ǝv�����ǁi���Â̐ՂȂ�Ăǂ��ɂ��Ȃ����j�B�B�B
�A�����J�ł͐�Β����ɂȂ�Ȃ��悤�ɋC�����Ă�������ǁi���̎��Â̂��߂̕ی��ɂ͓����Ă��Ȃ������̂ŁA��Β����ɂ͂Ȃ�Ȃ����A�Ɓi���Ɂj�C�����������Ă����j�A�A�����Ă���͂����ł��Ȃ��Ȃ��Ă����Ȃ��B���ꂩ��C�����悤�B
��Ȃ̕��́A���͌����̌��ʁA�E��0�C2�@����0�C7�@�Ƃقډ�����ԁB�ዾ�͒�w�N�̂����͕K�v�Ȃ��ƌ�����B����̌��f�͗��N�̏t�ŗǂ��Ƃ̎��B�ȑO�̐f�ËL�^����u�ڂ����䂩�����肵�܂��H����o���Ă����܂��傤���H�v�ƐϋɓI�i�Ɍ������j�Ɍ���ꂽ�̂ŁA�u�\�h�̂���ł��v�Ɛ�������_����2�{�w���B
���Ȃł́A�u�i����͒����j�\�h�̂��߂̖�������ɓh��܂��傤�v�Ɛ�������A����Ƀt�b�f�h�z����1�i���邢�͂���ȏ�̕p�x�j�ł�����肵�Ă���悤���B�Ȃ��ȑO�����A�\�h�̂��߂̎��Â�ϋɓI�ɂ���Ă����ۂ����B���ȉq���m�̕��́A���q�Ɂu���͗�������v�ƔO�������Ă������A�����s�����ǂ����́E�E�E�H
�����Ȍ���ł͂Ȃ��������A8���̎��������B���ʂ͍��i�B�����Z�A���Z�A�����Z�ł́A�����Z���������Ԉ���Ă����B���Z�͖��_�B���������7���̃e�L�X�g�ɓ���B
�����Z�́A5��1��1��4���A�ǂ��炪�����傫�����Ŗ������������̂ŁA�܂��܂����K���K�v�̂悤���B1��4�̂ق����A����������������̂ˁB
�����͕a�@�����1���̑唼���g���A�w�K�͂����̂݁B�a�@�̑҂����Ԃ�����قǒ����ƁA��ɂ��`�B
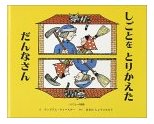 ���݂���Ă���ʐM���ށu�ł�������̎Z���N���u�v��D���ނɓ������B�����Ō�����4�N���������Ǝv�����A�������3�N���̃��x���B
���݂���Ă���ʐM���ށu�ł�������̎Z���N���u�v��D���ނɓ������B�����Ō�����4�N���������Ǝv�����A�������3�N���̃��x���B
��������Ă������ނ́A�u�]��̂�����Z�v�������Ă����B�ȒP�Ȃ��Z���̂́A�����Ő�ɂ���Ă����̂ŁA�����g���Ă��Z�̓����o���邱�Ƃ��A�ł�������̋��ނōĊm�F���邱�Ƃ��ł��ėǂ����K�ɂȂ��Ă���B
���{���̊w�K��
�ł�������3��
���w�Z�̏h��i����1��j
���̑��v�����g4��
���{���̓ǂݕ��������Ǐ���
�E�����Ƃ��Ƃ肩��������Ȃ���
�E �����b�v�X�̂킭�킭��`�� (1)
�E3�N���̎Z���̂Ђ݂�
�E �퍑�喼�̑����\�퍑���� ���w�ٔŊw�K�܂� (1)
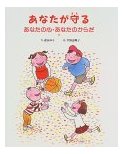 ���{���̓ǂݕ��������Ǐ���
���{���̓ǂݕ��������Ǐ���
�E���Ȃ������ ���Ȃ��̐S�E���Ȃ��̂��炾
���w���ď��߂Ẳ^����I������B���q�ɂƂ��ẮA���܂�Ă���2�x�ڂ̉^����B
���߂Ắi�N���̎��j���������ł́A�X�^�[�g���Ă����ɑ��̎q�̌C���E����Ƃ����n�v�j���O���N���āA���̎������Ă����q�ǂ������S���������~�܂��Ă��܂��A�����ɂȂ�Ȃ������B
�A�����J�ł́A���X���������͂���Ă����悤�����A�^����Ƃ������̂͂Ȃ������B
����́A6�l�ő����Č��ʂ�5�ʁB�Ō�܂Œ��߂��ɑ������̂ŁA�Ȃ�Ƃ��ʼn��ʂɂȂ�Ȃ������B
��Q�������́A�ŏ��̕��ϑ�̂Ƃ���ŏ��ʂ��قڌ��肷��d�g�݂ɂȂ��Ă����B6�l�ŃX�^�[�g���ĕ��ϑ��2�䂵���Ȃ��̂ŁA�ŏ��ɕ��ϑ�����I�����q���f�R�L���ɂȂ�킯���B���q�͂��̕��ϑ�ɏ�鑈���ɕ����Ă��܂��A���̎��_�ŕ������ӎ��������q�́A��肩�������ϑ䂩���э~��A���̂܂ܓ˂������čs���Ă��܂����B�B�B�i�I�C�I�C�j�ȁ`��ɂ��A�������Ă��Ȃ��q���B�B�B����4�ʂɏI���A�Ȃɂ���Ă��˂��B
���q�̗c����������ۂɎc��^����ł����B
 ���{���̓ǂݕ��������Ǐ���
���{���̓ǂݕ��������Ǐ���
�E�m���r�������������� ���_�Ђ̂悤�˂�ǂ���
���q�Ɂu������m���ăO���O���L����IQ�m�\�`�F�b�N�v�Ƃ������̂������Ă݂��Ƃ���A���q�̎v�l�^�C�v�����̂悤�Ȍ��ʂɂȂ����B���ׂĂɂ����ăp�[�t�F�N�g�ɉ���Ɓu���\�p�˃^�C�v�v�ɂȂ�炵���B
�ȉ��A���ʕ\���ł��B
�w�m�\�w���͂P�S�O�ȏ�Ɛ��肳��܂��B
�T�O�A�}�`�A�L���̒��ł́A�T�O�y�ыL���I�ȗ͂ɗD��Ă��܂��B
�v�l�A�L���ɂ����ẮA�v�l�͂ɗD��Ă��܂��B
�܂��A���ȂƂ��Ă͍���E�Z���E���ȁE�Љ��킸�A���Ƃ̗͂ƋL���I�Ȑ��̗͂��g���A�o�����X�悭�͂����邱�Ƃ��ł���Ǝv���܂��B
���\�͂������o���ɂ́A���Ƒ��œ����Ȃǂ̊G�̃J�[�h���L�����A����Ă�Q�[�����s�Ȃ��܂��傤�B���̂̌`�ł��ڂ���͂�L�����Ƃ��ł��܂��B
���݂̗D��Ă���͂�L���A������͂ƂȂ�u���M�v�Ɍ��т��Ă����Ă��������B�x
���q�́A������}�`�̒Z���L����b����K�v�����肻�����B
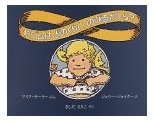 �ŋ߂ɂȂ��Ă悤�₭�A��ԊG�{�E�ǂ��G�{�Ƃ����̂��ǂ��������̂Ȃ̂��m��悤�ɂȂ�܂����B���܂ł́A�������q�ǂ��̍��ǂ��̂���i�o���Ă���j�G�{��A�y�[�W���p���p���Ƃ߂����Ă݂ẴC���X�s���[�V������\���̊G�Ȃǂ����ߎ�ɂȂ��Ă��܂����B
�ŋ߂ɂȂ��Ă悤�₭�A��ԊG�{�E�ǂ��G�{�Ƃ����̂��ǂ��������̂Ȃ̂��m��悤�ɂȂ�܂����B���܂ł́A�������q�ǂ��̍��ǂ��̂���i�o���Ă���j�G�{��A�y�[�W���p���p���Ƃ߂����Ă݂ẴC���X�s���[�V������\���̊G�Ȃǂ����ߎ�ɂȂ��Ă��܂����B
���������܂Ŏ������ڂɂ������̂Ȃ��ǎ��ȊG�{������������Ƃ������ƁA�܂����q�ɓǂݕ��������Ă��Ȃ��G�{������A�Ƃ����v������A�ĂъG�{�̓ǂݕ��������ĔR���܂����B
�������u�ւ������v�u��S���͂ǂ̂��炢�̂т邩����H�v�u�������Ȃ������Ȃ������v��ǂ݂܂������A�u�������Ȃ������Ȃ������v�ȊO�͏��߂Ă̊G�{�ł����B
���q�́u��S���͂ǂ̂��炢�̂т邩����H�v���C�ɓ������悤�ł��B
���ݒ���I�ɑ��q�̃N���X�̓ǂݕ������ɓ����Ă��܂����A�ǂݕ������̕���Ȃǂł��낢��w�Ԃ����A�ǂݕ�������������x�e�N�j�b�N���K�v���Ǝv���悤�ɂȂ�܂����B�I���Ɋւ��Ă��A���l���œǂޏꍇ�ƁA�N���X�Ȃǂ̏W�c�œǂޏꍇ�Ƃł́A�I�ѕ�������Ă��܂��B
����1�N���̎q�ǂ��B�ɓǂݕ����������Ȃ���A���ꂩ��2�N���A3�N���Ɛ������Ă����̂����Ō��鎖���o����̂��y���݂ɂ���̂Ɠ����ɁA���낢��ȊG�{���ꏏ�Ɋ��\���Ă������炢���ȁA�Ǝv���܂��B
��������Ƃł�������̃e�X�g�����܂����B3�~1���̂����Z�M�Z�ł��B�W�����Ԃ̋L�ڂ͂Ȃ������̂ł����A1���30�b���炢�����Ă���Ă����̂ŁA���\���Ԃ�������܂����B1����������̂�10�b���������v�Z�ɂȂ�܂��B
��������Z�̊T�O�ɓ���܂��B
�p��̃v���C�x�[�g���b�X���́A���߂Đ搶�̐��^���e�[�v���g�p���鎖�ɂȂ�܂����B�搶�����q�Ɍ����Ď���𓊂������܂��B���̎��������Ă���A�m�[�g�ɓ������L������`�ɂȂ�܂����B
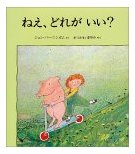 ���{���̓ǂݕ��������Ǐ���
���{���̓ǂݕ��������Ǐ���
�˂��A�ǂꂪ ����? �����}���فE�G�{�̕���
���e�̏�������싅�`�[���̎����������s���A���̑ł��グ���䂪�Ƃōs���܂����B
������甃���o���ƕ����̕Еt���ɒǂ��܂����B�����o���͈�l�ōs�����̂ŁA�傫�ȃJ�[�g�Ƀr�[�����H�����R����ς�ŕ����Ă���ƁA���w�����u�������E�E�E�v�ƂԂ₢�Ă��܂����B
���v15�l�Ƃ�����l���Ȃ̂ŁA��̂̕��ʂ���������܂���B��������̐H�ׂ���̗ʂ�15�{�Ƃ���ƁA�����̓�����p�ӂ��Ȃ���Ȃ�܂���B��������`���肪���ɒN�����Ȃ����߁A���ׂĂ̗p�ӂ͎���l�E�E�E�B
����́A�A�����J�Ŋw��ł����؍��ē��ɂ��܂����B����̃^���ɒЂ������������C���ŁA���̑��́A�Ă���Ƀ`�a�~��i�����Ȃǂ�p�ӂ��܂����B
���q�́A�͋������Z�������������Ƃ����̂ŁA�ꏏ�ɑ��o������Ă��炨���Ɗy���݂ɂ��Ă����悤�ł��B���o�Ɏn�܂�A�艟���Ԃ�n�����b�N�ɂȂ��ėh��ꂽ��A�n�[�h�ȗV�т��J��Ԃ�����Ă�����đ喞���A�������ɖ�̓R���b�Ɩ����Ă��܂��܂����B�j�̎q���āA�̗͗L��]���Ă܂��ˁ`�B
�܂��A�����ɏI����ėǂ������B�B�B�z�b�ƈꑧ�ł��B
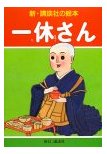 ���{���̓ǂݕ��������Ǐ���
���{���̓ǂݕ��������Ǐ���
��x���� �V�E�u�k�Ђ̊G�{
�v���Ԃ�Ɍ������̂���h���}�ł����B�ŏI��́A�Ȃ����܂��E�E�E�B
���̖͂ڂ��C�ɂ��鎖�Ȃ��A�����̋����ӎu�ł����Ď��g�ގp���A�����čŌ�̎q�ǂ������̌��ӕ\���̃V�[���A�u���̎q�B�A���������Ȃ��`�v�Ɗ������Ă��܂��܂����B�i�H�I���̎��������ɁA�����̐l���������Ő�u�Ԃ��āA�Ȃ����l���Ȃ���h�L�h�L���Č��Ă��܂��܂����B
�u�������߂Ȃ��I�v���̌��t�A���̃n���O���[�����A���̎q�ǂ��B�ɖ₢������e�[�}���Ǝ��͎v���܂����B��������߂Ȃ��A����������߂Ȃ��A�l����������߂Ȃ��E�E�E�B���̂��߂ɐ^���ɂȂ��Ă���p���A������������Ɗ����܂��B
�Ƃ���ŁA�����̂��W�����v�e�X�g�́A4������n�܂��č����6��ڂɂȂ�܂����B���̕ӂ肩��A�����Ԃ�ƃ��x�����オ�����Ȃ��A�Ɗ����Ă��܂��B�Z���́A���̐}�`�̕\������A���낢��Ȍ`�i���ʐ}�`�j�ȂǁA�}�`���炯�ł����B�ŋ߁A�w�Z�̏h�蓙�Ōv�Z�������Ă����̂ŁA���̎�̏o��͋v���Ԃ�Ɏ��g�݂܂��i���Ă������A���������̂������������Ɏ��g��ł��Ȃ����A�o���o���ł��ˁj�B
���ɍ��ꂪ��������B�Ō�́u���b�̑����������Ă݂悤�v�ł́A��������Ƃ��Ђ�����Ԃ肻���ɂȂ�܂����B20���ŁA���̖��Ɏ��g��ɁA����Ȃɂ�����������̂��낤���B�B�B
���e�I�ɂ��Ȃ荂�x�ɂȂ��Ă����̂ŁA�{�������Ď��g�ޕK�v�����肻���ł��B
�u���̂͂��킽��ׂ��炸�v�B������Ȃ�Ɠǂ݂܂����H�ƂȂ��Ȃ��ł��B
�g���r�A�̐�ŁA���̖������w�Z���T�����q�ǂ�����100�l�ɏo�����Ƃ���A���������̂�100�l��0�l�B��x����̂Ƃb��N���m��Ȃ������Ƃ������Ƃ��B
���w�Z�ɓǂݕ������ɍs���Ă��Ċ��������Ƃ����A������u���肮��v�̂悤�Ȑl�C���̂̊G�{�́A��Ԃ������S���ēǂݕ������o������̂��B�݂�ȍD���ȊG�{������A�n�Y�����Ȃ��A�Ƃ����z��̂��ƂɎ��M�������ēǂގ����o����B
�Ƃ��낪�N�����m���Ă������Ȑ̘b�Ƃ������̂́A�u����͒N�ł��m���Ă��邾�낤�v�ƍl���A�ĊO���O���Ă������ɋC�Â��B�S�̂ǂ����ŁA�u�����ǂނƁA�N�����w�܂�Ȃ��`���x�ƌ����o���̂ł͂Ȃ����H�v�Ƃ����ꖕ�̕s�����ǂ����ɂ��邩�炩������Ȃ��B
�������A���̂ƂȂ��Ȃ��̘b�́A���l���ł͂Ȃ��Ǝv���B���q���A��x����̊G�{�́A�A�����J�ɂ܂Ŏ����Ă������̂��i�A�j���G�{�����ǁj���A�u���̂͂��킽��ׂ��炸�v�̎��͏�����Ă��Ȃ������̂ŁA�m��Ȃ������̂��i�ꉞ���q�ɂ��A���̂Ȃ��Ȃ����Ƃʼn����Ă݂āA�ƌ�������A������Ȃ��A�ƕԎ�����Ă��܂��܂����j�B�B�B
���̓����͂܂������Ă��Ȃ��̂ŁA�Y�ꂽ���ɁA�䂪�Ƃɂ����x����̘b��������Ă���{��ǂݕ��������Ă݂悤�Ǝv���B
���w�Z�̓ǂݕ������ɂ��A�I�[�\�h�b�N�X�Ȑ̘b���Ђ������čs���Ă݂悤�B
��ɂ͎Q��܂����B�B�B�������A�}���K���B����w�Z���玝���A�������̃h���������Ă̊��z�ł��B�����̗��K���Ƃ͂ƂĂ��v���Ȃ����B���ȏ���Ђ�����Ă��邿���Ƃ������m�Ȃ��ǁA����Ŋ������g�ɕt���́H�H�H���Ďv���܂��H
���K�ʂ����|�I�ɑ���Ȃ��B1���ɂ�4�����K�ł��Ȃ��m�[�g�B�����m�[�g�Ƃ��ʂɍ���āA�������肷��̂��Ȃ��B����͊w�Z�C���ɂ��Ă��Ă͂����Ȃ��A�Ǝv���m�炳��܂����B��������R�搶�̖{�������Ȃ��A�[���B
�Ƃ���ŁA�ł�������̃v�����g�ł͉������Ă���̂����A�����O��̕��͑�̃v�����g�ŏ��߂Ďg�p�����B���̑g�ݗ��ĕ������ݍӂ��Đ������Ȃ���ꏏ�Ɏ��g�̂����A�u�{���ɂ���ō����Ă�́H�v�Ƒ��q�͔��M���^���������炾�i�����E�E�j�B�������邱�Ƃ����m��Ȃ��������q�́A�u�����������I�v�Ɗ����������������A���������o���Ă����߂Ȃ�ˁA���̕��͑�́B
�ł�������̉�������Ɓu�i���ꂳ��̐������j�ł�������̏������̂ق���������₷���I�v�ƈꌾ�B�܂��A���Ƃ̂����������A�������w��łق����Ƃ��낾�B���w3�A4�N�����炢�܂łɂ́A�������킹�����ꂳ��ɂ��Ă��炤��������Ȃ��āA�����ʼn����Ď����œ������킹������Ƃ���܂łł���Ƃ����ȁA�Ǝv���Ă���B
�����ŁA�ł���������v�旧�ĂĎ��g�߂�Ƃ���܂œ����Ă�����悤�ɁA������Ǝ��̕����H�v���Ȃ��Ƃ����Ȃ����낤�B
���{�̉^����́A��ς��Ǝv���B�s�i�̗��K�Ɍh��̎d���A�O�Ȃ炦��x�߂̌`�܂Ō��܂��Ă��āA�����m��Ȃ����q�͖����V�������Ƃ̘A���ŁA����͋��H�̎��Ԃɓf�����炵���B������ꂪ���܂��Ă���悤���B����2���Ԃ̑̈�́A���������̉��V���ł͓��ɑ�ς��������낤�Ȃ��B
�^������͊y���݂ɑ҂��Ă��邱�ƁA���Ȃ��̎p�����ɍs���̂��҂��������A�݂����Ȃ��Ƃ�b������A�Ί�ɂȂ����B
�܂��܂�1�N���A�\������Ă����疞�����Ă��邩�����łȂ��������ɕ�����B�������̂��B�^����̗��K������ĂˁB�����ǁA���q�̎�������^����O���������ɂȂ��č��M�I�Ƃ��ɂȂ肻���ŐS�z�ł��B�B�B
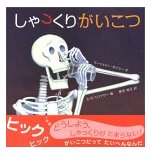 ���݂���Ă���ʐM����u�ł����̎Z���N���u�v���n�߂Ė�2�N�B�n�߂́A�C�O�Ƃ̂��Ƃ�ŕs���Ȗʂ�����������ǁA���q���ɓ��{����͂��������A�y���݂������B
���݂���Ă���ʐM����u�ł����̎Z���N���u�v���n�߂Ė�2�N�B�n�߂́A�C�O�Ƃ̂��Ƃ�ŕs���Ȗʂ�����������ǁA���q���ɓ��{����͂��������A�y���݂������B
������͂��߂�A���ނ���̃X�^�[�g�ŁA���݂�D���ނɓ������Ƃ���B1���ނ�8�����ł��Ȃ����v�Z���B1�P�����1���������Ă���Ă��邱�ƂɂȂ�B������40���łƂĂ�������肵���y�[�X�����A�n���ɑ��������BB4�ŃT�C�Y�̃v�����g���A���̑傫���Ƃ����K�x�ȗ]���Ƃ������q�ɂ͂��傤�Ǘǂ��v���B�悭�ǂ܂Ȃ��Ƃł��Ȃ���肪�����̂ŁA��������l����͂����Ă��ꂽ�炢���ȁB
����V���������Ă����w�K�ނ̒��ɁA���Z�������Ă����B�����ƕ��s���Ăł���̂ŁA������ʂŊw�ׂ�B
�����́A8���̎������������ɂ���\�肾�����̂����A�����\�����ݒ��ߐ�̎��_�ŁA���q��8��������Ƃ͐搶���v��Ȃ������悤�ŁA�\�����݂�����Ă��Ȃ������悤�������B����������͋[�����ł́A8�����i���C���������Ă����Ƃ̂��ƂŁA11���ɍs����7���̎������܂��傤�A�Ƃ������ƂɂȂ����B8���͏Ȃ�����ǁA7������͏o�܂��A�ƌ���ꂽ�B8�������Ȃ������͎̂c�O�ł������A����炤�̂��ړ��Ă݂����ȂƂ���̂��鑧�q�Ȃ̂ŁA7���ł͂�����Ă��炢�܂��傤�B
<���q���������낢�ƌ������{>
�E�ӂ���ɂ����ꂽ���Ƃ��̂��\�t�����X���b
�E��������肪�������
�����͏O�c�@�c�ψ����U���I���̓��B�Ƒ��ŏo�����Ă��܂����B
���ƂȂ����҂Ă邩�ǂ����S�z�������̂ł����A���v�ł����B
���{�̑�����b�����Ƃ́A���q���m���Ă���̂ł����A
���̑��I���j���[�X���G�T�Ɂi�H�j�A���ɂǂ�Ȃ��Ƃ�b������ǂ��̂��l�������Ǝv���܂��B
���q�̋����́A�u�N�ɓ��ꂽ�̂��H�v�Ƃ������Ƃ�����������܂��E�E�E�B
�i����̎s���I���ł��A����������������܂�������j�B�����E�E�E�B
�����O�A�A�����J�ŋN�����e�����A�ǂ��������ɋN�����̂������ꂽ���ߐ��������Ƃ���A�u���႟�A���{���푈������Ă����Ƃ��A��s�@�ɏ���ē˂����́i���U�j�Ɠ������B�v�ƌ����Ă��܂����B���U�̘b�́A�I��̓��ɂ�����8��15����1�x�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����A���̂��ƂƃA�����J�̃e�������т��Ȃ�āA�q�ǂ��̃A�^�}�͐^�����ȃL�����o�X�̏�ԂƓ����Ȃȁ[�A�Ǝv���܂����B�����ɂǂ�ȐF�̊G�̋���̂��Ă������A�ƒ닳��̐ӔC��������o�����ł����B
��������A�����ł��Z�ɓ���܂����B
�����̘b���ł����ǁB�S�[���f���E�B�[�N��������K���n�߂�5�����ځA�悤�₭���Z�ł��B�e�L�X�g��4���ڂ�����Ă��܂��B
�Ƃł̕��K���厖�Ȃ̂ŁA��������������Ă��܂��B
�ł��W���͂��Ȃ��̂ŁA1�N�[���ɂ��ʂ�5��Ƃ�8��Ƃ��ɂ��āA��������N�[�����J��Ԃ����@�ł���Ă��܂��B�����ꏏ�ɂ���Ă���̂ŁA�������^�_�ŏK���Ă���悤�Ȋ��o�ł��B
�{���͒ʂ��������������₵�������A�����ƐL�т�̂��Ǝv���܂����A������ŏT2���x�ł��B
�Ƃɂ������́A�����R�c�R�c�����邱�Ƃ����ł��B�N���ɂ͂ǂ̂��炢�܂ł����邩�A�ڕW�𗧂ĂĎ��g�ق������q�����荇�����o��Ǝv���̂ŁA�b�������Ă݂悤�Ǝv���܂��B
2�w���ŏ��̂����̎��ƂŁA�u10�܂ł̂�������@100��v������Ă������q�B1�w���ł��A1��̎��Ƃł�������Ƃ̂Ȃ��ʂ��A�����Ȃ����Ă���̂ŏ��X�т�����B�v�킸�u�搶�����S�}�X�v�Z���̂�����H�v�ƂԂ₢���B
���q�́A�u�S�}�X�v�Z���ĂȂɁH�v
���q��25�}�X�v�Z�͂�������Ƃ��邯��ǁA�S�}�X�͂�������Ƃ��Ȃ��̂ŁA�܂����m�̐��E�Ȃ̂��B�S�}�X�v�Z�ɂ��Đ�������ƁA�u���`�I�����Ȃ̂��I�ނ����������I�v�Ƃ̕Ԏ��B���̗ʂɈ��|����Ă���悤�B
���́A�ȑO����̃}�X�v�Z��������Ƃ��A���q�Ɂu�c�Ɍv�Z���Ă����Ă�����B�v�Ƌ����Ă����B�{���͉��Ɍv�Z���Ă������m�炵���̂����A������鐔�����X�ɕς��v�Z���P��������K�v���������Ȃ������̂ŁA�����ďc�ɑ����悤�ɑ������̂��B
���q�̕Ԏ����ƁA�}�X�v�Z����������Ǝ��̂��܂�o���Ă��Ȃ��悤�Ȃ̂Łi�܁j�A����͉��ɑ������Ƃ������Ă��������ȁA�Ǝv���Ă���B
�v���C�x�[�g���b�X���ŏo���A���߂Ă̏h��B����́u�G�{�̃Z���e���X�������ʂ��Ă��邱�Ɓv�B
�Ȃɂ����珑���R�g������������ق����������Ǝv���āA�搶�ɐ���Őf���Ă݂��̂����A���ꂶ�႟�Ƃ������Ƃ� ���̏h������Ă��邱�ƂɂȂ����B
����́uI can Read�v�V���[�Y�̒�����I�o�B�uI can Read�v���������ɂ����B
���ׂĂ̕��͂��uI can read�E�E�E.�v�Ŏn�܂��Ă���̂ŁA�������K�ɂ͂Ȃ�̂��ȁH�ǂ߂Ă������Ȃ��Ƃ��납��̏o���Ȃ̂ŁA���̂��炢���Ó����ȁA�Ǝv���B
���炭���̃V���[�Y�̒�����I��ŁA����Ă݂悤���ȂƎv���Ă���B
����Ɖp��4�����邩�ǂ����A�܂��v�Ē��Ȃ̂����A�Ƃ肠�����ߋ��������Ă݂Ă���l���悤�B5�������������Ԃ������̂ŁA���q�ɂ͂��Ɠ�������E�E�E�B
����w�Z����A���Ă������q�̊�͐��ꐰ��Ƃ������m���������A������[����1�{�̓d�b������܂ł������B���q�����F�B�̗m���̃{�^�������������ă{�^�������Ă��܂��A���̋�����l���炫���̂��B
���܂ʼn��x�����̎q�ɂ�����������o���Ă����炵���A���̎q���炻�̓s�x��������Ă�������l�́A���Ɋ��E�܂̏�����Ă��܂����̂��B
�b���̓��e���炷��ƁA���q�����̎q�Ɏ��X�ɂ����������Ă���Ɗ������悤�ŁA�������߂��Ă���Ǝv���Ă���悤�������B
�܂����F�B�Ƃ̃g���u�����o�ŁA���������F�B�̂��m����j�����͒f���ċ�����Ȃ��B���F�B�̂���֎f���A����l�ɂ�����ƎӍ߂̌��t�𑧎q�̌����猾�킹�鎖���厖���Ǝv���A�[�����f�������B
����̂���l�͑��q�̊��m��Ȃ������̂ŁA�������߂đ��q�̕\�������ƁA�u������邻���Ȋ�ł͂Ȃ��ˁv�ƌ���ꂽ�B���F�B�ɂ������ł�����̂ł͂Ȃ����Ƃ𗝉����Ă����������悤�ŁA����������������悤�������B���q�̑ԓx���܂��܂��c���i�e�\�ȁj���ƂŁA���낢��ȕ��ɂ����f�����������Ă��邱�Ƃ��ӂ�A���q�𗝉����Ă��炤�ɂ́A�܂��܂��������Ԃ������肻�����Ǝv�����B
���悢��2�w�����n�܂�A�Җ]�́i�H�j���H���X�^�[�g�B
�����͊w�Z�ŁA�e�q��������̉Ȋw�����������J���ꂽ�B�C�ӎQ���̂��߂��A���Ȃ������B
���e�́A�u�n���J�`�̍i����߁v�u�t�̒��f�̎����v�u���o�����v�u�X���C�����v�������B
�t�̒��f�ȊO�́A�ǂ�����܂ł�������Ƃ̂�����e�ŁA�u�n���J�`�̍i����߁v�Ɏ����Ă͉ċx�݂̍H��Ƃ��ďo�������̂ƑS�������������B
�t�̒��f�̎����́A-200���̒��f�i�t�́j�ɃS���{�[���E��e�j�X�{�[���E�ԁE�o�i�i�Ȃǂ�Z���āA���̌�ǂ��Ȃ邩��ڂ̑O�Ō��鎖���o���āA�����┏�肪���x�������N�������B
���o�̎����ł́A�Ö��E�����E�_���E�ꖡ�E���ܖ��̈��ݔ�ׂ�A����3���Ԑ|�ɒЂ��Ċk���n�������Ƃ̗��������Ă��ꂽ��ƁA���q���I�n�����C���B
���T����́A�����^����������̈�̎��Ƃ�2���Ԃقǂ���̂ŁA��͑����Q�Ȃ��ƂˁB
Special thanks to �������f���ɂ߂�
build by phk-imgdiary Ver.1.22